教員・研究一覧
教授
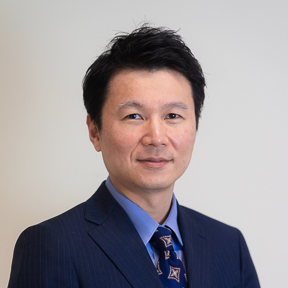
川原 圭博 教授
本郷キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: 電子情報
Embodied AIとIoTで創出するスマート社会の実現
私たちは、「Embodied AI(身体性を持つ人工知能)」と「Internet of Things(モノのインターネット)」の融合を目指した研究に取り組んでいます。AIを搭載したロボットが物理環境でのセンサ情報を手がかりといて、実世界とインタラクションすることで、柔軟で高度なタスクを可能になる世界の実現を目指しています。AIを活用したデジタルものづくり技術、無線給電技術、ロボット、センシング技術を開発し、さらにセンシング情報と基盤モデルを統合することで実世界の理解を深め、持続可能な社会を実現します。
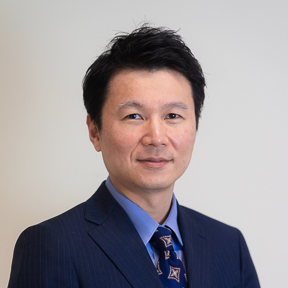
川原 圭博 教授
Embodied AIとIoTで創出するスマート社会の実現
私たちは、「Embodied AI(身体性を持つ人工知能)」と「Internet of Things(モノのインターネット)」の融合を目指した研究に取り組んでいます。AIを搭載したロボットが物理環境でのセンサ情報を手がかりといて、実世界とインタラクションすることで、柔軟で高度なタスクを可能になる世界の実現を目指しています。AIを活用したデジタルものづくり技術、無線給電技術、ロボット、センシング技術を開発し、さらにセンシング情報と基盤モデルを統合することで実世界の理解を深め、持続可能な社会を実現します。

工藤 知宏 教授
柏キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: ー
ネットワークとコンピューティングの真の融合を目指して - リアルワールドデータ活用を支える情報基盤 -
Cyber Physical System(物理世界と仮想世界を融合したシステム)には、情報基盤が必要であり、計算資源とネットワーク資源を連携して制御・利用する必要があります。例えば、現実空間とメタバースのインタラクションにおいて、リアルワールドデータのフィードバックをストレスなく行うためには、エッジデバイス、クラウド、MEC(Multi-Access Edge Computing)などの計算資源とそれらをつなぐネットワークをどう使うか問題です。このようなリアルワールドデータの活用を支える情報基盤技術の研究を行っています。

工藤 知宏 教授
ネットワークとコンピューティングの真の融合を目指して - リアルワールドデータ活用を支える情報基盤 -
Cyber Physical System(物理世界と仮想世界を融合したシステム)には、情報基盤が必要であり、計算資源とネットワーク資源を連携して制御・利用する必要があります。例えば、現実空間とメタバースのインタラクションにおいて、リアルワールドデータのフィードバックをストレスなく行うためには、エッジデバイス、クラウド、MEC(Multi-Access Edge Computing)などの計算資源とそれらをつなぐネットワークをどう使うか問題です。このようなリアルワールドデータの活用を支える情報基盤技術の研究を行っています。
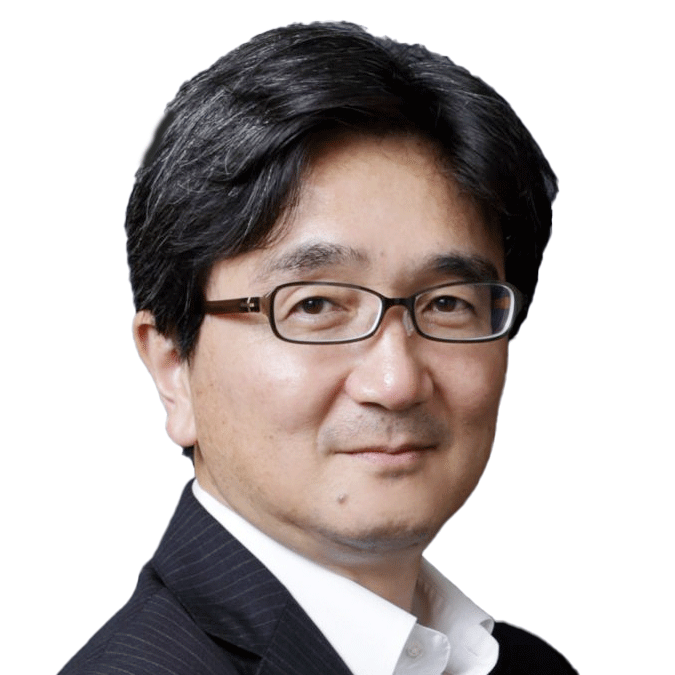
森川 博之 教授
本郷キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: 電子情報
デジタルで社会・産業・経済・地方を変える
デジタルが社会をどう変革していくかに想いを巡らせながら,5G / Beyond 5G / 6G,モノのインターネット,クラウドロボティクス,無線通信/給電,情報社会デザインなどの研究を進めています.しなやかな若い発想で一緒に研究を進めていきましょう.
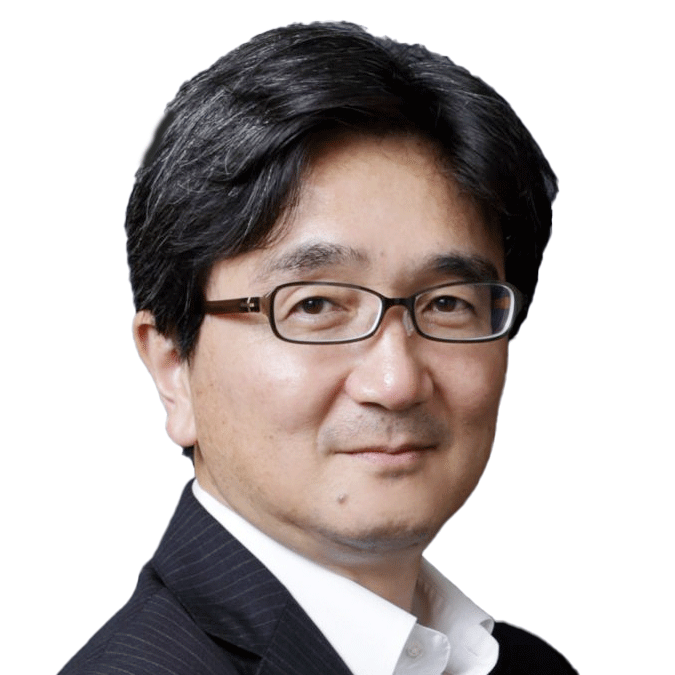
森川 博之 教授
デジタルで社会・産業・経済・地方を変える
デジタルが社会をどう変革していくかに想いを巡らせながら,5G / Beyond 5G / 6G,モノのインターネット,クラウドロボティクス,無線通信/給電,情報社会デザインなどの研究を進めています.しなやかな若い発想で一緒に研究を進めていきましょう.
准教授
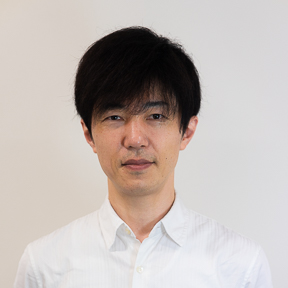
小川 剛史 准教授
柏キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: ー
ヒト×モノ×コトのインタラクション
拡張現実感や仮想現実感の技術を用いて人々の能力を拡張し、日常の生活を豊かにすることを目標に、さまざまな研究に取り組んでいます。研究テーマに共通するキーワードは「つなぐ」。人と人をつなぐ「コミュニケーション支援」や「グループウェア」、人とコンピュータをつなぐ「インタフェース」、人とデータをつなぐ「インタラクション技術」など、ヒト×モノ×コトを、それぞれ相互に作用させることで、新たな体験を創出する仕組みを実現します。
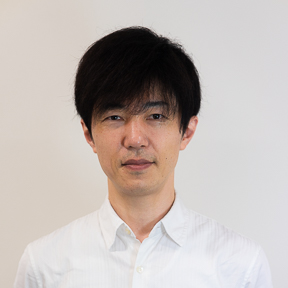
小川 剛史 准教授
ヒト×モノ×コトのインタラクション
拡張現実感や仮想現実感の技術を用いて人々の能力を拡張し、日常の生活を豊かにすることを目標に、さまざまな研究に取り組んでいます。研究テーマに共通するキーワードは「つなぐ」。人と人をつなぐ「コミュニケーション支援」や「グループウェア」、人とコンピュータをつなぐ「インタフェース」、人とデータをつなぐ「インタラクション技術」など、ヒト×モノ×コトを、それぞれ相互に作用させることで、新たな体験を創出する仕組みを実現します。
近藤 大嗣 准教授
柏キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: ー
高セキュリティを担保するネットワーク基盤技術に関する研究
現在、多くの企業は標的型攻撃やDistributed Denial of Service攻撃などのサイバー攻撃の対象となっており、その影響は当該企業のサービスを利用するユーザにまで波及しています。こうした社会的課題となっているサイバーセキュリティの問題に対し、ネットワーク構造や通信プロトコルに加え、インフラの運用実態といった多角的な視点からその解決を目指した研究に取り組んでいます。
近藤 大嗣 准教授
高セキュリティを担保するネットワーク基盤技術に関する研究
現在、多くの企業は標的型攻撃やDistributed Denial of Service攻撃などのサイバー攻撃の対象となっており、その影響は当該企業のサービスを利用するユーザにまで波及しています。こうした社会的課題となっているサイバーセキュリティの問題に対し、ネットワーク構造や通信プロトコルに加え、インフラの運用実態といった多角的な視点からその解決を目指した研究に取り組んでいます。

中村 遼 准教授
柏キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: ー
社会を支えるネットワークとソフトウェア
データを運ぶネットワークと、データのやりとりを行うソフトウェアは、現代社会のさまざまな分野において欠かせないものとなりました。インターネットのような広域通信ネットワークはその代表例です。また現代の情報サービスを実現するには、複数のコンピュータをネットワークでつなぎ、分散処理する必要があります。私たちは、絶え間ない発展を続ける情報システムを支え、多様な要求、性能、そして信頼性を実現するネットワークとソフトウェアの研究を行っています。

中村 遼 准教授
社会を支えるネットワークとソフトウェア
データを運ぶネットワークと、データのやりとりを行うソフトウェアは、現代社会のさまざまな分野において欠かせないものとなりました。インターネットのような広域通信ネットワークはその代表例です。また現代の情報サービスを実現するには、複数のコンピュータをネットワークでつなぎ、分散処理する必要があります。私たちは、絶え間ない発展を続ける情報システムを支え、多様な要求、性能、そして信頼性を実現するネットワークとソフトウェアの研究を行っています。

中山 雅哉 准教授
柏キャンパス
大学院: 工・電気系・(※)
学科: ー
広域分散処理
様々な機器がネットワークを介して接続する現在、それらを繋ぐためのネットワーク基盤技術だけでなく、各種機器から情報をどのように集め、どのように処理し、どのように活用するかといった応用技術まで、あらゆる分野の領域を横断して、新しい研究課題にチャレンジしています。

中山 雅哉 准教授
広域分散処理
様々な機器がネットワークを介して接続する現在、それらを繋ぐためのネットワーク基盤技術だけでなく、各種機器から情報をどのように集め、どのように処理し、どのように活用するかといった応用技術まで、あらゆる分野の領域を横断して、新しい研究課題にチャレンジしています。

成末 義哲 准教授
本郷キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: 電子情報
無線と未来を考える
サイバーフィジカルシステム(CPS)を最⼩限の⼈的コストで設計・構築・運⽤する“ゼロコン フィグレーションCPS”の実現に向け、次世代無線⽅式およびフィールド指向コンピューティングの研究開発を展開しています。

成末 義哲 准教授
無線と未来を考える
サイバーフィジカルシステム(CPS)を最⼩限の⼈的コストで設計・構築・運⽤する“ゼロコン フィグレーションCPS”の実現に向け、次世代無線⽅式およびフィールド指向コンピューティングの研究開発を展開しています。

矢谷 浩司 准教授
本郷キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: 電子情報
インタラクティブなシステムで新しいユーザ体験をデザインする
ユーザインタフェースの研究を通して,情報技術を活用した新たなアプリケーションを提案するとともに,インタラクティブなシステムが人間の行動や意思決定にどのような影響を与えるかを研究しています.

矢谷 浩司 准教授
インタラクティブなシステムで新しいユーザ体験をデザインする
ユーザインタフェースの研究を通して,情報技術を活用した新たなアプリケーションを提案するとともに,インタラクティブなシステムが人間の行動や意思決定にどのような影響を与えるかを研究しています.