教員・研究一覧
教授

塙 敏博 教授
柏キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: ー
次世代スパコンへの道を切り拓く
スパコンは従来のシミュレーションに加えて大規模機械学習を実現するプラットフォームとしても注目されています。これらを協調させることでもっと高度なアプリケーションを実現できます。そのためには通信やファイル入出力などあらゆる処理を最適化する必要があり、より進んだこれらの融合・協調により、次世代スパコンの基盤技術の開発を目指します。

塙 敏博 教授
次世代スパコンへの道を切り拓く
スパコンは従来のシミュレーションに加えて大規模機械学習を実現するプラットフォームとしても注目されています。これらを協調させることでもっと高度なアプリケーションを実現できます。そのためには通信やファイル入出力などあらゆる処理を最適化する必要があり、より進んだこれらの融合・協調により、次世代スパコンの基盤技術の開発を目指します。

峯松 信明 教授
本郷キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: 電子情報
喋って聞いて教えてくれるコンピュータを用いた音声コミュニケーション支援
音声のテキスト化(音声認識)、テキストの音声化(音声合成)はスマホでも動く時代になりました。これらの音声技術を使って、人と人、人と機械間の、より質の高い音声コミュニケーションの実現を支援する枠組みを構築しています。音声工学以外にも、音響音声学、認知科学、言語学、脳科学など、様々な知識を身につけ、音声コミュニケーションを営む方々のQoLの向上を目指しています。

峯松 信明 教授
喋って聞いて教えてくれるコンピュータを用いた音声コミュニケーション支援
音声のテキスト化(音声認識)、テキストの音声化(音声合成)はスマホでも動く時代になりました。これらの音声技術を使って、人と人、人と機械間の、より質の高い音声コミュニケーションの実現を支援する枠組みを構築しています。音声工学以外にも、音響音声学、認知科学、言語学、脳科学など、様々な知識を身につけ、音声コミュニケーションを営む方々のQoLの向上を目指しています。
准教授

大石 岳史 准教授
駒場キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: ー
実世界の時空間モデリング・表現
ロボットや自動運転車両などの自律移動を実現するために、LiDARやカメラなどの光学センサデバイスを用いて実世界の3次元モデル化、認識、解析する技術の開発を進めています。

大石 岳史 准教授
実世界の時空間モデリング・表現
ロボットや自動運転車両などの自律移動を実現するために、LiDARやカメラなどの光学センサデバイスを用いて実世界の3次元モデル化、認識、解析する技術の開発を進めています。
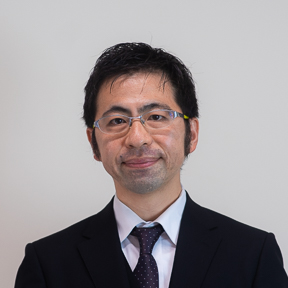
齋藤 大輔 准教授
本郷キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: 電子情報
実データ指向の音声情報処理とメディア情報処理
齋藤研究室では音声情報処理の要素技術の発展・高精度化・応用を進めるとともに、それを軸としたマルチメディア情報処理について研究開発を行っています。特に近年では複数人歌唱などの複雑な歌唱現象やロボットの見た目と音声の関係性に関する分析など実世界の複雑な音現象を対象とした研究に取り組んでいます。研究スタンスとしては数理的なバックグラウンドに基づいて新しい技術を創造し、幅広く様々なメディアを取り扱うことを目指しています。
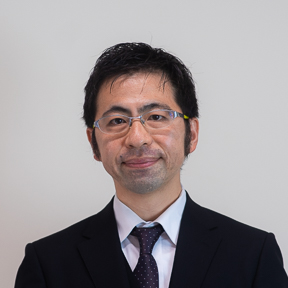
齋藤 大輔 准教授
実データ指向の音声情報処理とメディア情報処理
齋藤研究室では音声情報処理の要素技術の発展・高精度化・応用を進めるとともに、それを軸としたマルチメディア情報処理について研究開発を行っています。特に近年では複数人歌唱などの複雑な歌唱現象やロボットの見た目と音声の関係性に関する分析など実世界の複雑な音現象を対象とした研究に取り組んでいます。研究スタンスとしては数理的なバックグラウンドに基づいて新しい技術を創造し、幅広く様々なメディアを取り扱うことを目指しています。

下川辺 隆史 准教授
柏キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: ー
スパコンにおける大規模シミュレーション
物理シミュレーションは、気象・宇宙・ものづくりなどの計算科学・計算工学の様々な分野で活用されています。次世代スパコンを活用した大規模シミュレーションの実現には、計算手法、アルゴリズム、ソフトウェア技術の研究開発が必要です。私たちは、流体計算、GPU計算、AMR、高速化手法、機械学習、動的負荷分散などの研究に取り組んでいます。

下川辺 隆史 准教授
スパコンにおける大規模シミュレーション
物理シミュレーションは、気象・宇宙・ものづくりなどの計算科学・計算工学の様々な分野で活用されています。次世代スパコンを活用した大規模シミュレーションの実現には、計算手法、アルゴリズム、ソフトウェア技術の研究開発が必要です。私たちは、流体計算、GPU計算、AMR、高速化手法、機械学習、動的負荷分散などの研究に取り組んでいます。
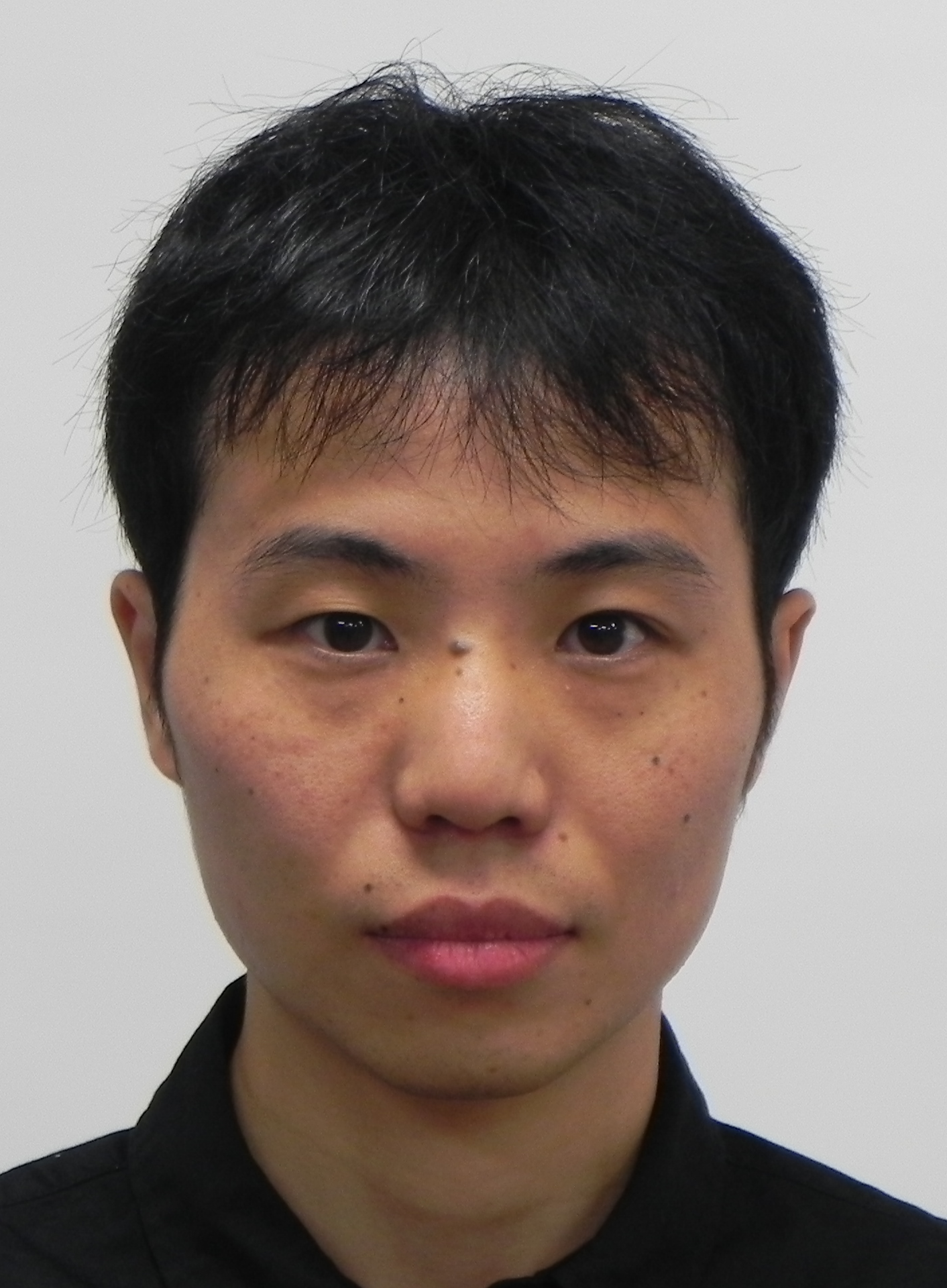
三木 洋平 准教授
柏キャンパス
大学院: 工・電気系
学科: ー
高性能計算と銀河考古学の協奏による宇宙のダークオブジェクトの解明
宇宙にはダークマターやブラックホールなどの直接検出できていないダークオブジェクトが大量に存在すると考えられていますが、多くの謎が残されています。私たちは、こうした宇宙の謎に迫るため、数値シミュレーションを用いた研究やコード開発に取り組んでいます。特にGPUを活用した高性能計算や、ベンダーニュートラルGPUコンピューティングの実現に注力しています。また、近傍銀河の詳細な観測データをもとに銀河の形成・進化史に迫る銀河考古学の手法も活かし、計算機科学と宇宙物理学を融合させた学際的な研究を進めています。
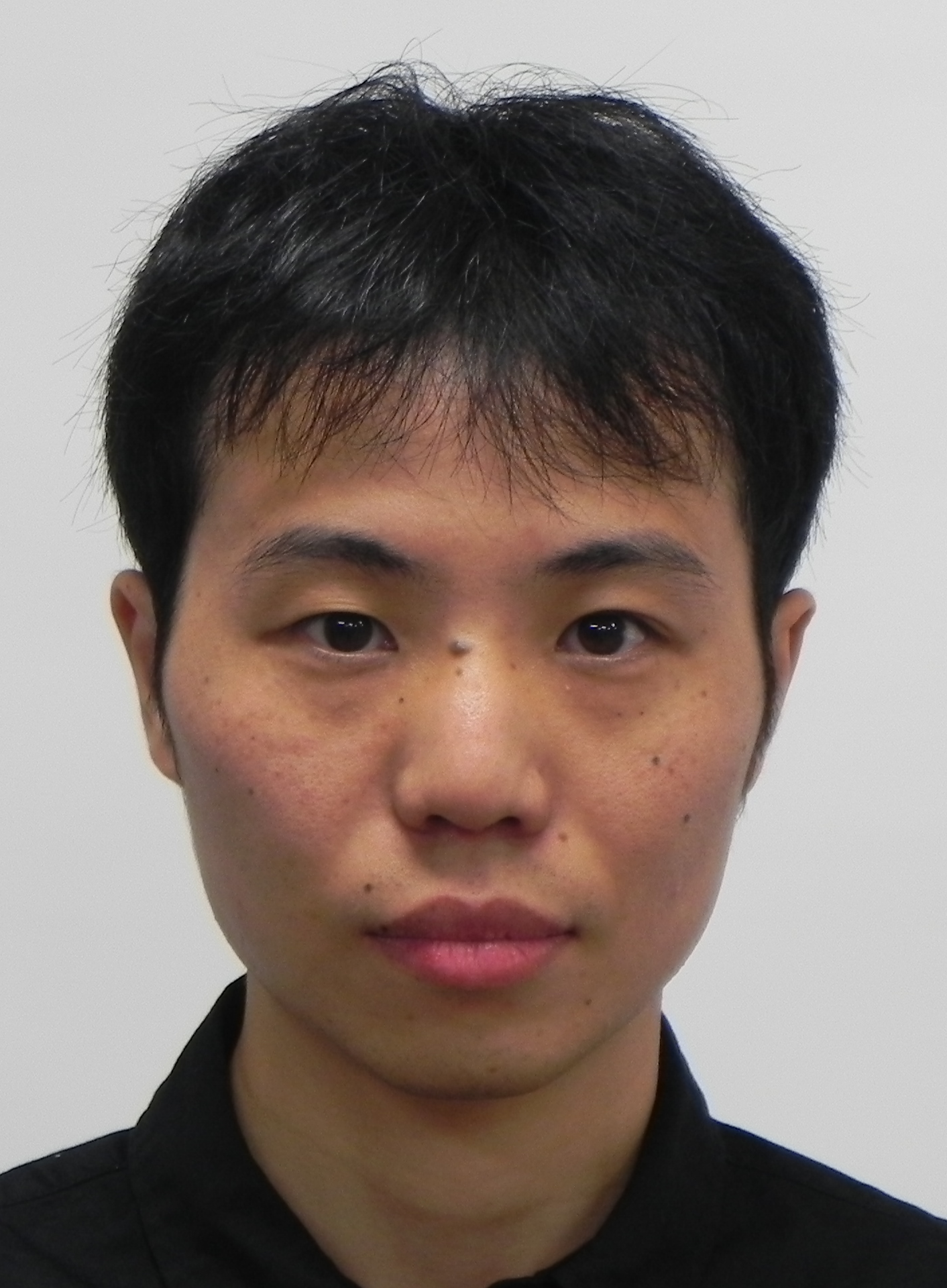
三木 洋平 准教授
高性能計算と銀河考古学の協奏による宇宙のダークオブジェクトの解明
宇宙にはダークマターやブラックホールなどの直接検出できていないダークオブジェクトが大量に存在すると考えられていますが、多くの謎が残されています。私たちは、こうした宇宙の謎に迫るため、数値シミュレーションを用いた研究やコード開発に取り組んでいます。特にGPUを活用した高性能計算や、ベンダーニュートラルGPUコンピューティングの実現に注力しています。また、近傍銀河の詳細な観測データをもとに銀河の形成・進化史に迫る銀河考古学の手法も活かし、計算機科学と宇宙物理学を融合させた学際的な研究を進めています。